- Column
- 今こそ問い直したいDXの本質
そもそも「DX」とは何なのか、その定義を問う【第1回】
DXの根本的な部分に納得していないあなたへ
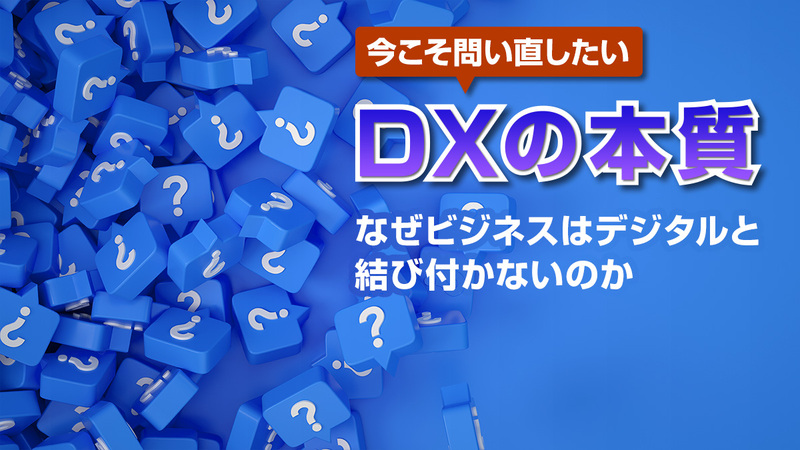
数年前までDX(デジタルトランスフォーメーション)関連書籍は、書店でかなりの面積を占めていましたが今や、その割合を大きく減らしています。Googleトレンドでも「DX」のWeb検索は2022年半ばがピークのようです。DXはもはや“オワコン(終わったコンテンツ)”であり、「ChatGPT」など生成AI(人工知能)技術の盛り上がりに押され、存在感が薄くなったまま消えゆく運命にあるのでしょうか。
「DX(デジタルトランスフォーメーション)」「デジタル変革」といった用語は今も、新聞やテレビなどで良く目にします。しかし結局のところ「DX」については「よく分からない」というのが多くの方の本音ではないでしょうか。
関連書籍などを見ても、何をすれば良いのかは漠然としており、どこに向かうのかも書かれていません。コンサルティング会社はコンサルやITベンダーがビジネスのために作り出した“虚像”ではないかという疑惑も拭えません。
その点、最近の「ChatGPT」(米OpenAI製)が口火を切った生成AI(人工知能)技術については、手放しで「素晴らしい」と思われていることでしょう。誰もが普通に文章の作成や要約に使え、それなりの品質の回答が瞬時に得られるなど、生産性は爆上がりです。
また同じ「X」系の「GX(グリーントランスフォーメーション)」や「SX(サステナビリティトランスフォーメーション)」に対しては疑義を唱える方は少なそうです。地球環境を保護するためにビジネスを変革することは、もはや単なる社会貢献ではなく、ビジネスの本来像になりつつあります。各社に不可欠な活動です。
DXブームの終焉の背景に情報技術に対する認識のズレがある
生成AIやGX/SXといった活動に比べると、DXという言葉からは、どうにも焦点が定まらない印象を受けるのではないでしょうか。IT導入の言い換えなのかどうかも不明瞭です。DXを推進する人たちも、変革を煽っておきながら、いざ取り組もうとすると「何がやりたいですか」と逆に聞いてくるだけです。
企業で働く個人にとっても、DXに関わるとキャリアが一気に不透明になる感覚があるかもしれません。「DX推進組織といっても、その立ち位置は不安定だし、スキルセットも会社の本流からは遠い。転職組がはしゃいでいるだけで、プロパーの人たちからは距離を置かれている印象もある。そんな中に飛び込んで得られる何かがあるとは、ちょっと思えない」といった印象ではないでしょうか。
DXが騒がれ始めてから何年も経ちますが「結局のところ何なのか分からない」と感じている方は少なくないでしょう。であればブームが終わるのは自然な流れだと思います。
ただ筆者には「DXが必要だ」という確信があります。では、ブームが終焉を迎えそうな今、何が問題だったのでしょうか。それは「今、世の中で何が起こっているか」に対する環境認識のズレに要因があると思っています。
『会社という迷宮 経営者の眠れぬ夜のために』(ダイヤモンド社)を著し、経営コンサルティング会社Corporate Directions(CDI)を設立した石井 光太郎 氏は、CDIのサイトに、こう書いています。
””技術(technology)といえば、経済学的には生産関数において生産性を決定づける因子であり、経済学者J.A.シュムペーターが経済発展の原動力たるイノベーションの重要な誘因としてきた通り、まさに競争相手に勝利し利益を生み出すoriginalityの源泉として、経営者が主体的にmanagementする要素であり続けてきました。
しかし、現代の急速に革新・進化する科学・技術は、その主客関係を逆転させ、むしろ経営は技術環境の急流の中を受動的に泳ぐことを強制されている、と言った方がもはや実感に近いかもしれません。“”
ここで言及されている「技術」はIT(Information Technology:情報技術)に限りませんが、世界の時価総額ランキングの変遷を見れば、近年でビジネスに最も影響を与えた技術が情報系であることは明らかでしょう。
つまり経営において、コントロール可能なツールだったITが、もはや否応なしに、ときには暴力的に影響を与え続けてくる環境になった。それを知覚している人にとっては「ITありきのビジネスに生まれ変わる」すなわちDXの必要性は自明です。
しかしITがどこまで進歩しても、それを“道具”だと思っている人には、AIやIoT(Internet of Things:モノのインターネット)を売り込むためのキャッチコピーにしか思えない。この違いがDXに対する態度を二極化させているのです。