- Column
- 今こそ問い直したいDXの本質
そもそも「デジタルとITは別物」なのか、インターネットとデータの意味【第2回】
DXの根本的な部分に納得していないあなたへ
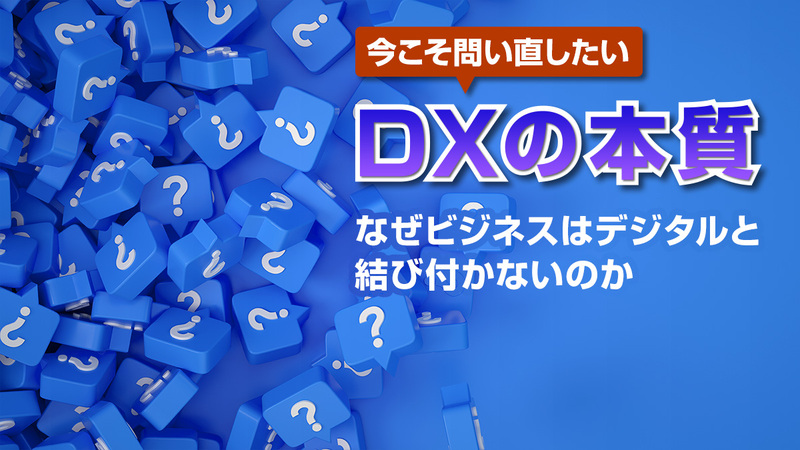
DX(デジタルトランスフォーメーション)の「D(Digital:デジタル)」とは、何を指しているのでしょうか。わざわざ「IT(Information Technology:情報技術)とは別の言葉を使う必要が、どこにあるのでしょうか?案外、DXにおける「デジタル」の定義は、どこにも書かれていないように思います。今回は、この「デジタル」について考えてみます。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の「D(Digital:デジタル)」という言葉は実際、かなり曖昧な形で使われています。例えば、DXを初めて定義したエリック・ストルターマン(Erik Stolterman)教授は、DXについて、こう述べています。
「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」 (『Information Systems Research』のp.687〜692、Erik Stolterman & Anna Croon Fors、2004)
彼は、デジタルとITを完全に同義として扱い、その浸透を「トランスフォーメーション」としています。
IT業界の周辺には「デジタル」を定義する動機がない
経済産業省によるDXの定義はこうです。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」 (『デジタルガバナンス・コード2.0』、経済産業省、2020)
力強い文言ですが、デジタル技術という言葉自体は定義されずに用いられています。「データ」とは別概念として扱わっている点も気になるところです。
実は、筆者がIT系調査会社のアナリストにヒアリングした際も「デジタルを明確に定義して用いているケースは少ない」とのことでした。しかし、このことは非常に気持ち悪くないでしょうか? 特に、これからDXに関わろうという人にとっては「何がデジタルで、何がデジタルではないのか」も分からないまま闇雲に学べと言われているようなものです。DXと称してあらゆるものを売り込んでくるコンサルティングファームやITベンダーに対峙するためには「自社にとって必要かどうか」の判断軸がなければ、混乱は避けられません。
ただ、「デジタル」を定義するという行為は、平等を旨とする省庁には向きません。定義とは領域を決める線を引くことですから、ITのなかにデジタルに含まれないものが出てきてしまうためです。そこで漏れてしまう製品/サービスを扱うITベンダーは猛反発することでしょう。
少しでも、いろんなものを売り込みたいプレイヤーが、わざわざ自分たちのビジネスを狭めるようなことも考え難いでしょう。企業内の情報システム部門ですら「DXと言えば予算が通りやすいから曖昧なままのほうが便利」といった理由でデジタルの定義には消極的かもしれません。
つまり、IT業界やITを直接扱う側には、デジタルを定義したいという動機が、あまり存在しないのです。「DXで自社ビジネスを良くしたい」という強い想いこそが、その目的や手段を明確化するためにDXを定義することへの唯一のモチベーションだと言えそうです。
“デジタル”の特徴は「つながる」と「データを使う」の2点
筆者は以前から「デジタル」を自分なりに定義しています。それは、技術面として「つながる」と「データを使う」の2つを満たすものです。第1回で「ITとDXの違いはインターネットだ」としました。インターネットの最大の特徴は「つながる」ことです。手紙や電話やFAXも双方向につながる技術です。現代のインターネットも、その延長線上にあると言えます。
インターネットは、「Web 1.0」(1990年代)の頃は、テレビやラジオと同じく“一対多のブロードキャスト”として捉えられていました。それが「Web 2.0」)2000年代)になると“多対多の双方向性”によって爆発的に普及しました。そのつながりは人類が初めて手に入れたものです。これにより大規模なブロードキャストから小さなコミュニティまでの世界中がオンライン上で接続されました。
インターネットの「つながる」力を象徴する例の1つがSNS(Social Networking Service)でしょう。個人間で、つながるのはもちろん、企業と個人の関係も変わりました。「インフルエンサー」という新たな職業を生み出したのもSNSです。新聞やテレビのようなメディアしかなかった時代とは大きく異なり、消費者や一般市民の声が社会に大きな影響力を与えるようになってきたのです。