- Column
- 今こそ問い直したいDXの本質
そもそもDXとは新規事業開発ではないのか?取り組み姿勢に関する15の想定問答【第7回】
DXの根本的な部分に納得していないあなたへ
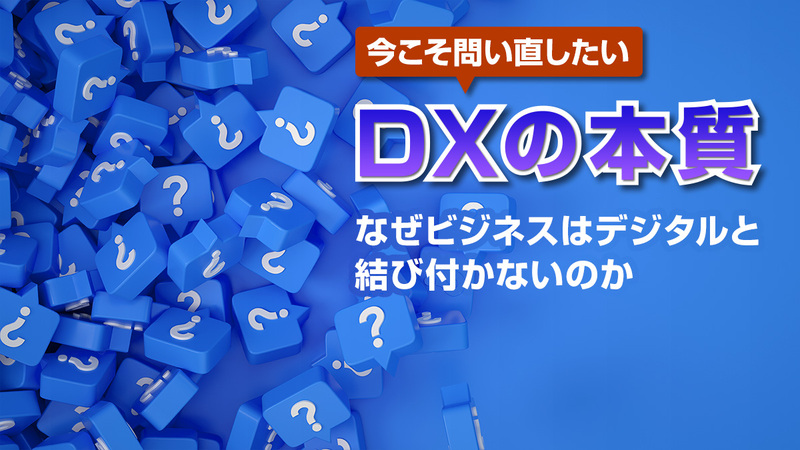
前回、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進捗はどう評価すればよいかを考え、「デジタルを機会と見做すマインドセット」が主要な要因だとの考えに至り、それを「digital attitude/openness」と呼びました。この概念を援用すれば、DXへの取り組みに関する代表的な質問にシンプルに答えられます。想定問答により「digital attitude/openness」の大切さを再確認したいと思います。
DX(デジタルトランスフォーメーション)は継続的な“長い長い”活動であり、DXへの取り組みが本当に進んでいるのかどうかは、単に1つのプロジェクトが成功したといっただけでは不十分です。そのため筆者は、その尺度として「デジタル化する社会への姿勢」を提案し“変化し続ける能力”がより重要だとしました。その変化し続ける能力の主要要因を「digital attitude/openness」と名付けました。
この概念を元に、DXへの取り組みや、その進捗に関して、多くのみなさんが抱かれるであろう質問を想定し、それぞれに答えていきたいと思います。
デジタルは“道具”ではなく“ビジネス環境”である
Q1:当社はDXに数年間取り組んできたが、本当に進捗しているのか?
A1 :digital attitude/opennessが高まっているならイエスと言えます。高まっていないなら局所的な効率化であるdigitalizationの域を出ていないので、デジタル社会への適応力には不安があります。
Q2:DXの成功は遠い将来の結果論なのか?
A2 :結論から言うとイエスでしょう。目的地もKPI(Key Performance Indicator)も実効性のある設定は難しいからです。だからこそ結果論ではない判断の軸が必要であり、digital attitude/opennessが有用と考えています。
Q3:デジタル技術は所詮は道具ではないのか
A3 :デジタルは、サステナビリティ、少子高齢化、為替変動などと同列で語られるべきビジネス環境です。それに対して情報システムは、生産設備や知的財産などと同じ道具だといえます。この視点から見たときに、ITが道具以上に見えておらず、社会の変化を感じ取っていないのであれば、digital attitude/opennessが低いということです。この質問自体がDXが進展していないことの証左ともいえます。
Q4:新しい技術に毎回飛び付くのに意味があるのか?
A4 :digital attitude/opennessが高いという意味でDX的です。結果的には意味がなかったかもしれませんが、変化を機会と見做すイノベーティブな風土が長期的な企業の存続・発展には重要だと考えます。ただし経営的な観点では、初期から多額の投資をするのではなく、イノベーションの基本に従って、確率が低いうちは薄く広く張ったほうがいいでしょう。
Q5:無知なままデジタルに前向きだと、コンサルに踊らされるだけでは?
A5 :そのとおりです。ですのでリテラシーを高めたり、社内に専門家を雇ったりするのは有用です。ただし、十分に準備をしてからDXに取り組むというのはお勧めできません。なぜなら、デジタルの進歩は速いので、準備はいつになっても完成しませんし、実際の体験から学べることも多いからです。重要なのは、準備という名の躊躇(ちゅうちょ)に陥らず、PDCAサイクルを小さく速く回し始めることでしょう。
“正解”を求める姿勢ではDXを継続できない
Q6:米国の企業はDXが進んでいるというが、個々のプロセスのデジタル化は日本のほうが進んでいるように見える。これはどういうことか?
A6 :個々のプロセスのデジタル化による効率化・自動化は、あくまでdigitalizationです。これを積み上げたとしても、社会の変化に鈍感なまま個別最適をしているのであれば、digital attitude/opennessは高まっていません。米国企業が、仮にデジタル技術の使いこなしで劣っているとしても、社会や顧客の変化を感じ取り、そこをビジネスチャンスと見て施策を実行しているなら、digital attitude/opennessが高い、すなわちDXが進捗していると捉えるのが良いのではないでしょうか。
Q7:この10年、「社会は変わる」と言われ続けてきたが、案外と変わっていない。DXはまやかしなのではないか?
A7 :DXは、社会にITが浸透していくことで起こる変化に対応することです。社会の全てが一律に変化する訳ではないため、10年経っても、ほとんど変わらない側面も存在します。重要なのは、扇動者の言葉に右往左往することではなく、先の読めない時代の変化に対応できる力を身に着けることです。別の言い方をすれば、digital attitude/opennessが高い人は、社会の変化している側面に注目し、チャンスがないか絶えずアンテナを立てているのです。
この質問だけに限ったことではありませんが、質問内容から“正解”を求めている姿勢が感じられることがあります。しかし、VUCAの時代に確かなものはありません。まやかしなどと批判するより、未来を作りにいくほうが建設的だと思います。とはいえ誇大広告が横行しているのは確かなので、自分の判断に自信を持つために不断の学習は必要です。
Q8:DXには取り組んでみたが、思ったより得られる利益が小さくROI(Return of Investment:投資対効果)も冴えない。当社の業態はDXには向いていないのではないか?
A8 :この問いを発している経営陣のdigital attitude/opennessが低いことがよく分かる質問です。ですが、経営陣がデジタルに懐疑的なら、トレンドに流されず、将来のITが自社にもたらす影響を低く見積もるのも一案です。歴史を振り返るなら、機械化を拒みながら産業革命を生き延びた手作業の企業もあります。
Q9:当社はデータ利用が浸透してきたが、DX先進企業と言えるのか
A9 :現時点ではイエスでしょう。ただし将来的に、データの使い方が固定化されてしまい、次第にプロセスが硬直化してしまうなら、digital attitude/opennessが下がったことを意味します。つまりDXが後退するという可能性もあるということです。