- Column
- 今こそ問い直したいDXの本質
そもそもDXの進捗はどう判断すれば良いのか?VUCAの時代の評価指標【第6回】
DXの根本的な部分に納得していないあなたへ
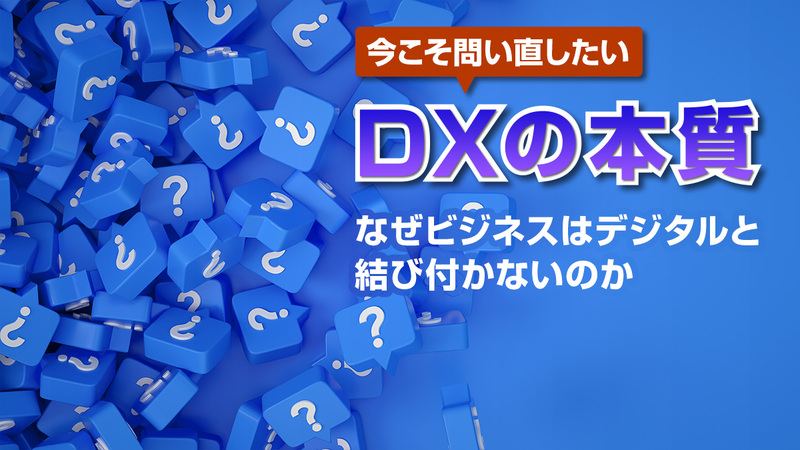
DX(デジタルトランスフォーメーション)の本質に迫るためにこれまで、DXの定義やデジタルとITの違い、DXの三段階理論などについて考えてきました。三段階理論の考察では、DXは“継続的な活動”であることが大切だとしました。しかし、継続的な活動であるとすれば、DXのための日々の活動が将来の企業変革につながっているのか、それはどう判断すれば良いのでしょうか。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の文脈において、デジタルの対義語を筆者は、アナログではなく「情報システム」だと考えています。端的に言えば、情報システムは“企業の道具”であるのに対し、デジタルとは「ITが社会にもたらす環境変化」です。そしてDXは、その環境変化に追随してビジネスを変え続ける取り組みだというのが結論です。
では、その変化し続ける継続的な取り組みの進ちょく状況は、どのように測定・評価できるのでしょうか。理想論で言えば、先に目指している“あるべき姿”を描き、バックキャスト(逆算)で方策を決めることで、進捗は評価できます。しかしVUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:あいまい性)の時代にあって、具体的な未来像を描くのは難しく、あるべき姿はどうしても抽象度が高くなります。
そうなると、目の前のデジタル改善活動(digitalization)と将来のあるべき姿の粒度が違いすぎ、DXの進展を未来像との距離で判断することは難しくなってしまいます。部分最適な仕組みを導入し小幅な業務改革を積み重ねていくことが本当にデジタル時代の企業存続・発展に寄与しているのかという疑問は拭えません。DX先進企業と、そうでない企業の差は何なのでしょうか。今、先進と言われている企業は何を獲得しているのでしょうか。
持続的な変革に取り組むには“危機”ではなく“機会”に着目する
こうした疑問およびDXへの継続的な取り組みに対して筆者は、ITに対する慣れと自信の獲得が重要だと指摘しました(第5回参照)。しかし、これだけでは、まだ腑に落ちないことでしょう。そこで、新たに2つの観点を取り入れてみます。1つは「なぜ米国企業は貪欲にITを取り入れるのか。それに対し日本企業の多くはなぜ様子を見ているのか」です。これは、一橋大学の伊藤 邦雄 先生との会話のなかで改めて認識したポイントです。
もう1つは、リーダーシップ論の権威であるジョン・コッター氏が企業変革を成功させるための3つの要素として新たに提唱した「人間の性質」「現代型組織のあり方」「リーダーシップ」に関する研究のうち、最初の「人間の性質」に関わるものです。
これら2つの観点は、実は行き着くところは同じです。危機と機会、すなわち環境の変化を忌むべき対処と見做すか、面白そうなことをする機会と捉えるかの違いが大きいと考えます。筆者はコッターから大きな影響を受けているのですが、DXの進捗を測るという観点とはつながっていませんでした。
米国企業に代表される、先進的なデジタルを存分に取り入れる企業には、新しいITやITによる社会の変化は、取り組めることがどんどん増え、可能性が広がる“面白いもの”に見えているはずです。
一方で出足が鈍く、デジタルをうまく取り入れられていない企業にすれば、速い変化も難しいITも、競争力を維持するために取り組まざるを得ない重荷に映ります。このマインドセットの違いが、新規事業への熱意や企業変革の難易度に影響してくるのです。
新規事業を「気の進まない片付け仕事」として始めて、うまくいくケースは想像しがたいでしょう。「イノベーションは遊びから始まる」と言われるように、好奇心と情熱が働かない対象では、挫折を繰り返す不確実な活動は、成功どころかまともに始まりすらしないと想像されます。
企業変革も同様です。コッターが主張するように、実は危機感だけで組織は変われません。防衛本能が強まってしまい、短期的な対処はできるものの、すぐにエネルギーを使い果たしてしまうからです。持続的な変革に取り組むには“危機”ではなく“機会”に着目しなければなりません。そのためには、ITは、さまざまな可能性を秘めたチャンスに見えている必要があるのです。
デジタルで大きく変化している他業界が他人事に見えている経営陣、顧客のデジタルシフトに気付かないマネジャー、新たなAI技術を業務に応用する方法が思い付かない担当者などなど。そんな布陣の企業ではDXへの準備が整っていないと言えます。