- Column
- 今こそ問い直したいDXの本質
そもそも「DXのための文化」があるか、オープンと学び・試すの価値【第3回】
DXの根本的な部分に納得していないあなたへ
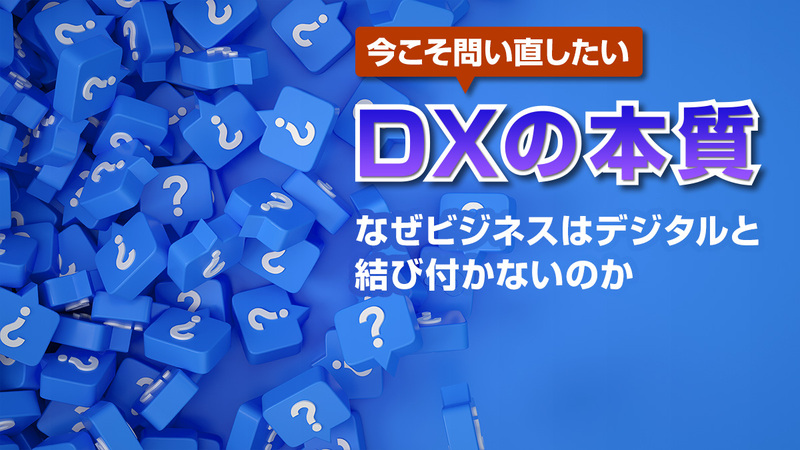
デジタルの専門家は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進において、会社の風土や仕事の進め方にまで口を出してきます。それはなぜでしょうか。ビジネス部門側からみれば、うっとうしくて仕方ないとか越権行為だなどと感じるかもしれませんし、デジタル部門の側にすれば異分野での成功体験の押しつけではないのかと気になるでしょう。DXに風土や仕事の進め方などの間に、どんな関係があるのかを考えてみます。
あるDX(デジタルトランスフォーメーション)の専門家は、経営者から「DXを始めるには何からすべきか」と聞かれた際に「ソフトウェア開発プロジェクトのオンライン管理プラットフォーム『GitHub』にアカウントを作ることだ」と答えたと言います。つまり「経営者自らがプログラムを書き、他者とコードをシェアすべきだ」ということです。なぜそんな発想に至るのでしょうか。
DXを推し進めるに当たって技術以外にも必要なものがあるかどうか。筆者なりの答えを先に述べるなら、DXの専門家がDXを推進に当たって風土やプロセス設計に口を出すことに妥当性はあります。しかし業績向上に対する確たるエビデンスがあるというよりも「デジタルの強みを活かし定着させるために必要だ」というのが正直なところです。
デジタルの文化的特徴の1つは「オープン」
デジタル的な風土・文化の中で、既に根付いているのが「オープン(公開)」です。現代のITでは、多くの仕組みがオープンになっています。誰でもがアクセスできるデータや、誰でも利用・改変できるプログラムのソースコード、自由なヘッドハンティングを可能にする履歴書などなど。いずれも数十年前には考えられなかったことです。
そもそも、なぜオープンにするのでしょうか。例えばライフサイエンス研究の世界では、遺伝情報のように取得したデータの公開は当たり前になっています。その結果、データを取得したチームが秘匿・死蔵していたら、まるで不可能だったようなイノベーションが相次ぎ、科学技術は目まぐるしい速度で進展しています。データの公開が社会の役に立つことは想像に難くないでしょう。
ですが、企業は社会の全体最適のみを目指している訳ではありません。仮に社会の役に立つにしても、株主の利益を大きく損なうような施策は取れません。せっかく資金を投入して得たデータや、作成したプログラムを公開すれば、競争優位は失われ後発プレイヤーを利するばかりです。
それでも企業が公開する理由は何でしょうか。実際、米国のIT企業でも必ず全てを公開する訳ではありません。オープンな文化が主だったデータサイエンスの世界でも、米OpenAIは生成AI(人工知能)サービス「ChatGPT」を基本的にはクローズドな形で提供しています。一方で米MetaはLLM(Large Language Model)の「Llama」をオープンな形で提供し、多くのプレイヤーがその改良に携わっています。今後どちらの方針が主流になるのか分かりません。
オープンにする最大のメリットは、Llamaに見られるように、プレイヤーが集まることです。その製品や関連技術を全て自社から提供するつもりであれば、オープンにする理由は弱くなります。しかし、自社製品を思いがけない形で使いこなし価値を高めてくれるような企業や、自社のファンとなって入社を希望する凄腕エンジニアがいたりするなら、公開する価値は十分にあります。つまり、オープンは、自社周辺にビジネスエコシステムを構築するためなのです。
全面的に公開しなくてもエコシステムは構築できます。OpenAIはAPI(Application Programming Interface)という形でChatGPTを他サービスと連携させる手段を用意し、興味深いエコシステムを既に形成しています。これは部分的なオープン戦略と言えます。ただ、オープンによってエコシステムを形成しながら、持続的な競争優位を失ってしまわないようにバランスさせていると考えては、オープンを見誤ります。
むしろ、持続的な競争優位という概念を捨て去り、一時的な競争優位を築き続ける経営方針と考えるべきでしょう。言い換えれば、競争優位を続けられるだけの速度を絶えず追い求めることがオープン戦略の特徴だとも言えます。これは、長期に亘って安定した競争環境を仮定しているポーターやバーニーの戦略論とは前提が異なることに注意が必要です。