- Column
- 今こそ問い直したいDXの本質
そもそも「情報社会(Society 4.0)」は本当に到来しているのか【第4回】
DXの根本的な部分に納得していないあなたへ
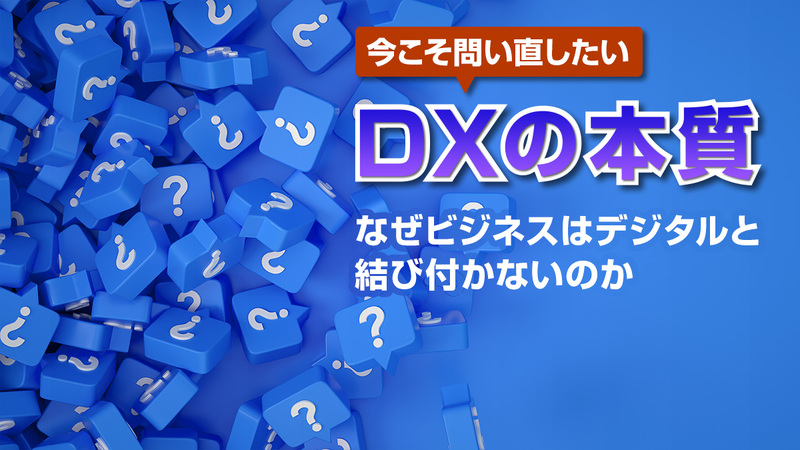
第2回で、政府が唱える未来社会の概念に「Society 5.0」に対し、筆者の認識では現状は本格的な情報社会にすら到来しておらず「Society 3.5」の状態にあると指摘しました。今回は、なぜ筆者が現状を「Society 3.5」だと認識しているかについて補足します。
政府が唱える未来社会の概念「Society 5.0」について、内閣府は「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会」だと説明しています。「5.0」とあるのは、狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会 (同2.0)、工業社会(同3.0)、情報社会(同4.0)に続く社会という意味です。
人類の歴史を狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会という形で区切っていくのは、未来学者アルビン・トフラー氏の影響を強く感じます。トフラー氏は1980年に発行した著書『第三の波』において「農業革命という第一の波によって狩猟社会が農耕社会になり、産業革命という第二の波によって工業社会が到来した。いま第三の波と共に情報社会が訪れつつある」と予言しました。ただ問題は、その情報社会が「どんな姿なのか」ということです。
現代社会は常に産業革命の影響下にある
経営学者のピーター・ドラッカー氏は産業革命の影響に関し「蒸気機関の出現が鉄道につながり、鉄道は銀行、郵便、新聞の出現をもたらした」と言ったとされています。ある革新的な技術やムーブメントは、影響が連鎖し社会を大きく変えていくという意味です。これはまさにイノベーションであり、それを予想するのは簡単ではありません。
蒸気機関の発明で有名なジェームズ・ワット氏は、自身の技術を守ろうと特許裁判に多くの時間を使いました。ですが蒸気機関が銀行や新聞にまで影響が及ぶことを見通せていたなら、その価値を最大化するために知的財産(IP:Intellectual Property)を囲い込むのではなく、新しい業態の企業を起こすという判断をしたかもしれません。
このように複雑で広がりの大きな話ですから、筆者に情報社会の完成形を予言する力がないのは自明です。ここでは未来予測に頼るよりも過去を振り返り、農業社会から工業社会への変化がどれほど大きかったかをヒントに考えてみましょう。
農業社会では、一般の人々は時計を持っていなかったとされています。作付けや収穫に関わるだけに暦に関しては非常に正確ですが、一日の労働において5分、10分のズレは何の問題もないからです。
人々が時間を気にするようになったのは、工場で同じ時間に集まり、働いた時間に応じて給料を受け取るようになってからです。それまでの農業社会では、必要に応じて早朝から働き、一仕事したら午睡を取るといった仕事スタイルだったようです。
均質な教育が実現したのも産業革命以降のことです。質の高い労働力を大量に確保するために教育が広く義務化されました。家庭の姿でいえば、それまでは大家族で農地の近くに住んでいたものが、工場労働に伴い核家族化や都市化が進みました。規則正しい1日3食の生活リズムの定着も同様です。大企業という存在自体、産業革命によって誕生したとされています。その意味では、階層型の組織や経営学のような学問も産業革命の産物です。
これらのほとんどが現在も継続して存在しています。そこから少なくとも言えるのは、現在の社会は数百年前からの産業革命の影響を大きく受けているのであって、何万年も続く人類の歴史を通した“普遍の姿”ではないということです。
つまり、次代である“真の情報社会”に進展したとき「現在の生活のどれが残り、どれが変わるのかは分からない」ということです。全員が同じ時間に出社し時間で給料をもらうのがいいのか、均質な教育が求められるのか、核家族が都市に住むのは幸せで効率的なのか、規則正しい1日3食の生活は何に効果があるのか、大企業というあり方が経済活動を支える主流の形なのか、階層型組織や今の経営学が情報社会でも継続するのか、などなど、いずれも現時点では明確な解はありません。